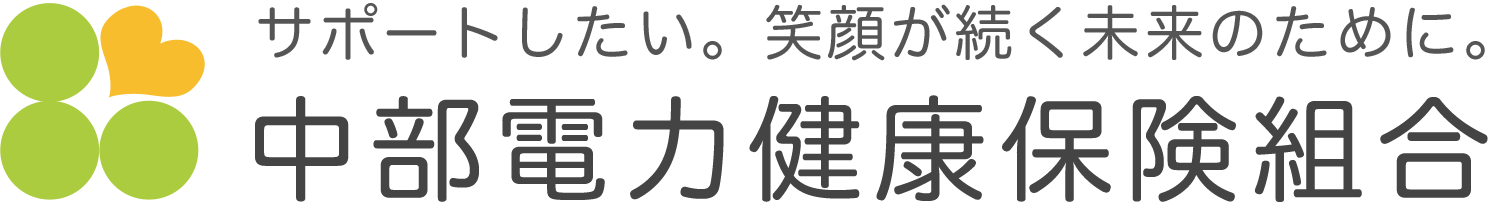マイナンバーカードに保険証情報が紐づけされている可能性がありますので、マイナポータルにてご確認ください。紐づけされている場合は資格確認書の交付はいたしません。
マイナポータルサイトhttps://myna.go.jp/の「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」欄から確認が可能です。
資格確認書紛失等の理由で再交付を希望する場合は、資格確認書滅失届を提出してください。
マイナ保険証取得後の資格確認書は、有効期限切れのものはご自身で廃棄してください。有効期限内のものは、資格喪失時に返却が必要なため大切の保管ください。もしくは、事業所へご返却ください。
資格確認書の有効期間中に退職もしくは当組合の資格を喪失する場合は、資格確認書を返却してください。家族が扶養から外れる際や、氏名変更届を提出する際にも、資格確認書を返却してください。
マイナ保険証で受診する場合は、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。(医療機関はオンラインで医療費負担割合が確認できるため)
こども医療証や重度障がい者医療証の提示はマイナ保険証で受診する場合でも必要です。
住民登録のある市区町村窓口で更新手続きが必要です。通知に従い、速やかに手続きをしてください。
なお、電子証明の有効期限が切れた場合は、有効期限が切れた日から3か月間はマイナ保険証を利用できます(ただし、保険資格情報の共有のみで診療情報・薬剤情報などを提供することはできません)
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の場合に限り、資格情報のお知らせ又はその写し、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険適用にて受診いただくことが可能となります。
マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。(https://web.hir.myna.go.jp/Accept/checkStatus)
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。
なお、「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示された場合は、当健保までご連絡をお願いします。
利用登録の申込みを行っても、利用登録処理が完了していない場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。
ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。
マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めています。
なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。
マイナンバーカードを取得されていない場合は、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を2025年12月1日までに交付いたします。(申請は必要ありません)そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
なお、使用できなかった旨を「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へご連絡をお願いします。
新たに資格を取得した方や氏名変更、定年再雇用、転籍の方など資格情報が更新された方に「資格情報のお知らせ」を交付しています。
「資格情報のお知らせ」は、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。マイナポータルでも同じ情報をご確認いただけます。通知書の内容をご確認いただき、ご自身が認識している情報と違う情報が掲載されていないかご確認をお願いいたします。
本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
マイナンバーカードのみでの受診が難しい医療機関(オンライン資格確認システム未導入の医療機関)の場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
- 「健康保険 被扶養者異動届・状況報告書」
- 離職票1と離職票2(本書)
- 源泉徴収票(写)・・・最新のもの
- 退職後任意継続をしている場合は、任意継続資格喪失証明書(本書)
上記書類が必要になりますが、提出できない書類があるなどの場合は、ご連絡ください。
また、上記書類以外にもご提出していただく場合がございますのでご了承ください。
基本的に法的書類は全て本書になります。
現在個人情報が含まれる書類のファックスでの授受は取り扱っておりませんのでご了承ください。
2025年12月1日で期限切れとなる健康保険証は、返却不要です。不正使用防止のため、期限切れ後は速やかに、氏名・記号・番号・保険者番号などの個人情報が読み取れないように、細断するなどして各自で適切に廃棄してください。
(2025年12月1日までに喪失される方は、事業所経由にて健康保険証をご返却ください。)
現在お持ちの保険証は2025年12月1日まで使用可能です。
任意継続被保険者の方で、有効期限が2025年12月2日以降の印字がある場合でも、2025年12月1日までの使用となります。
健保から振込をさせていただく際の口座となります。
健保給付金等につきましては、在職中は会社を通じて振込させていただいておりましたが、退職後に健保から直接振り込ませていただくためにご提出いただいています。
いいえ、二重払いではありません。
在職中の保険料は翌月払い、任意継続の保険料は当月支払いのため同月に2度のお支払いとなります。
いいえ、基本的には変更はできません。
やむをえない場合のみの取り扱いとなりますので、事前によくご検討くださいますようお願いいたします。
いいえ、任意継続期間は2年間のみです。
期間の延長などはありませんので、期間満了後は国民健康保険へのご加入となります。
いいえ、使えません。
在職中の保険証は、退職日の翌日から無効となりますので、退職日にご返却ください。
任意継続の保険証は、入金確認後、退職日以降にご自宅へ簡易書留にてお届けします。
原則は2年間ですが、以下の場合は喪失となります。
- 保険料が未納の場合
- 被保険者が死亡した場合
- 被保険者が就職した場合
中電健保より喪失日の3週間くらい前に自動的に「資格喪失通知書」を送付させていただきます。
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で、喪失後14日以内に加入の手続きをしてください。
また「資格喪失証明書」が必要な方は、当組合までご連絡ください。
退職日の10日前から受付できます。
はい。ただし、ゆとり勤務と分かるよう空欄に記入してください。
就職する予定がある方は、毎月支払いを選択ください。前納6ヶ月、12ヶ月を選択しますと割引が適用になります。
就職する予定がある方は、コンビニ払いが望ましいです。2年間続けて毎月支払いを選択する方は、銀行口座振替を選択してください。
受診していただくことはできません(人間ドック等健診の補助対象となりません)。扶養除外日以前であれば、受診いただけます。受診されない場合は、ご自身で医療機関にキャンセルの連絡をしてください。扶養除外日以降に受診された場合は、全額自己負担となります。
75歳の誕生日の前日までは受診できます。誕生日から後期高齢者医療制度へ加入するため、中部電力健康保険組合から脱退することになります。
ワクチンの予防効果は約5ヵ月間と考えられていますので、12月上旬までに早めに接種しておきましょう。
保険診療ではないため、医療機関が個々に料金設定を行っています。2,000円~4,000円程度ですが、総合病院は比較的費用が高い傾向にありますので、受診前に医療機関でご確認ください。
1名につき予防接種1回のみ補助対象となりますので、2回目以降は全額自己負担となります。ただし、1回目の接種が2,000円未満の場合、2回分を合計し、上限額まで補助します。2回分の領収書を画像添付のうえ電子申請してください。また、愛知県内にお住まいの方は「接種補助券」を廃棄してください。
自治体に乳幼児、小児を対象とした助成制度がある場合は併用が可能です。まずは、市区町村で費用補助の申請手続きを行ってください。その後、補助額が確認できる書類(①支給決定通知、②補助額が記載された領収書)を画像添付のうえ電子申請してください。
中電健保の被扶養者の方で65歳未満の方(65歳の誕生日の2日前までの接種)であれば、対象となります。65歳以上の方については、自治体の補助を受けることができますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
自治体の補助は“65歳の誕生日の前日から適用”とされているため、誕生日の2日前までに接種された場合は対象になります。
接種者全員の名前と料金を追記してもらってください。
毎月25日までの電子申請について、翌月20日(休日の場合はその前日の営業日)に各事業所の健保給付支払口座に振り込みとなります。事業所によっては、振り込み日が異なる場合がありますので、事業所の担当者にお問い合わせください。任意継続被保険者は、退職時に申請のあった指定口座に振り込みいたします。支払いの状況については「Pup Up医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」にてご案内いたします。
※11月~1月は申込が集中することが予想されます。電子申請の内容確認は受領順に実施しますが、支給については1ヵ月遅れることがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。また、電子申請に不備があった場合についても同様となります。
被保険者と被扶養配偶者です。
中電健保[e-mail]jigyou@chudenkenpo.or.jpにご連絡ください。本人確認用コードをメールにてご連絡させていただきます。連絡の際には、「Pep Up本人確認用コード」問い合わせ票兼回答票をご利用ください。
皆さんに配付させていただいた「健康情報サービス登録方法のご案内」をご確認ください。中電健保のホームページ内「健康づくりに役立つ!」「健康情報ポータルサイト Pep Up」からも確認できます。
資格取得日から概ね2カ月後に、被保険者は、事業所へ、被扶養配偶者は、ご自宅に届きます。
手続きの必要はございませんが、以下については資格喪失から91日後よりご利用いただけなくなります。
-
- 健保からの通知や、健保主催のイベントへの参加
- 「私の健康状態」の更新
- 「医療費通知」・「ジェネリック通知」の閲覧
詳しくは、「PepUp よくある質問 その他質問」をご覧ください。
ご自宅のパソコンやご自身のスマートフォンで、インターネットブラウザをご利用頂く場合に、ご登録のID=メールアドレス、パスワード(ご自身で設定する、任意のパスワード)をご入力頂ければ、閲覧可能です。
3ヶ月に一度(3,6,9,12月)、配信され、公開月の第3週月曜日(祝日の場合は翌日)に更新されます。更新情報については、ご登録のメールアドレスに、更新した旨のお知らせを配信いたします。
健診結果データの反映までに、概ね2~4カ月程かかります。更新情報については、ご登録のメールアドレスに、更新した旨のお知らせを配信いたします。
健診結果(メタボリックシンドロームに関連性の高い「特定健康診査」の12項目)の数値を使用して算出した総合的な健康度を健康年齢で表しています。
健診結果がない、または健康年齢を算出する項目が不足している場合は、表示されません。
本人の健康状態に即した記事は、毎月1日に更新されます。更新情報については、ご登録のメールアドレスに、更新した旨を配信いたします。
また、毎週火曜日(変更することがあります)に1記事程度、記事が追加されますのでご確認ください。
健康記事を閲覧したり、イベントに参加いただくなどでポイントが貯まります。
新規登録、健康記事は、閲覧すると即時付与されます。それ以外については、実施月の翌月以降に付与されます。
Pep Up内にありますPEPポイントのページで、交換したい商品をご指定いただき、交換することができます。
ポイント付与日から3年後の月末に失効します。
ただし、資格喪失した場合は資格喪失から91日後に失効します。
詳しくは、「PepUp よくある質問 ポイントについて」をご覧ください。
この調査は、被扶養者として認定されたときの状況が、現在も維持されているかどうかを確認し、みなさまの大切な保険料を公正に運用するために毎年実施しているものです。被扶養者の資格を継続するために必要な手続きでございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 法的な根拠は以下のとおりです。
- 健康保険法施行規則第50条
「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
コールセンターにて電話で聞き取りをしながら代行入力していただけますので、コールセンター(050-2030-7859)までご相談ください。また、どうしても不可能な場合は紙での提出も可能ですので、その場合は事業所健保担当までお問い合わせください。
就学中でアルバイトをしている場合は「③学生」と「②パート・アルバイト等の給与収入」どちらにもチェックをつけてください。
「⑦自営業者」にチェックをつけてください。
夫婦は極めて強い生計維持関係にありますので、扶養家族に入っていない方の収入状況を状況報告書に記入していただいております。これは、お母様の「主たる生計維持者」がお父様と被保険者のどちらなのかを確認させていただくためです。
調査対象にお名前がある全ての方に回答が必要です。ただし、今年になって認定された方は添付書類が省略できますので、システム内「職業・収入」選択画面で「❹2025年1月以降に新たに被扶養者となった方」のみにチェックしてください。ただし、退職等が理由で扶養認定された方で雇用保険について「④雇用(失業)保険受給」、「⑤雇用(失業)保険受給手続き中(申請延長手続き含む)」、「⑥雇用(失業)保険受給しない」に該当する場合はそちらもチェックが必要です。(④、⑤をチェックした方は雇用保険受給資格者証の添付が必要です。)
年金の種類と収入を確認するためです。
所得証明書に掲載されているものは、前年の証明(※)になりますので、今年の年金収入を証明する書類として提出をお願いしています。
※所得証明書は各年の1月1日~12月31日までの1年間の所得を証明するものです。
年金振込通知書の再発行については、ねんきんダイヤル及び年金事務所等で受け付けています。(年金事務所のHPより)
被扶養者認定時に確認させていただいた事業収入が被扶養者の収入基準(19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満[年額]、60歳未満(19歳以上23歳未満以外)は130万円未満[年額]、60歳以上または障害年金受給者は180万円未満[年額])を満たしているかを確認するためです。
事業収入は、“収入-売上原価-その事業に要した直接的必要経費=生計を維持するために投入し得る収入”となりますが、所得証明書に掲載されているものは経費等が控除された後の金額になるため、収入の全容を確認することができません。
そのため、収入、原価、経費の全てが確認可能な確定申告書(控)一式の提出をお願いしています。
第一表、第二表の他に、「青色申告決算書」または「収支内訳書」もセットでご提出くださいますようお願いします。
※「青色申告決算書」または「収支内訳書」の内容より、事業に要した直接的必要経費か否かを審査しております。
別居の被扶養者との生計維持関係を確認するために提出をお願いしています。そのため、仕送金額は被扶養者の収入以上であることが条件となります。
被保険者が(誰が)被扶養者に(誰に)いつ、いくら送金を行ったかを確認させていただきます。銀行振込の利用明細、振替受付票等を4か月分(5月~8月)ご提出くださいますようお願いします。
別居の被扶養者については、毎年必ず確認させていただきますので、大切に保管しておいてください。
エクセルを画像化していただき、極力画像で添付してください。
被保険者により生計が維持されている扶養家族であるかを確認するため、提出をお願いしています。1か月の世帯全体の支出のうち、費用負担状況についてご記入ください。
費用負担されているのであれば、中電健保の被扶養者ではなくてもご記入ください。
所属事業所健保担当箇所までお願いします。
中部電力健康保険組合 適用・給付チーム(電話:052-880-6202)までお願いします。
コールセンター(TEL:050-2030-7859)〔平日10:00~17:00〕(12:00~13:00除く)
※WEBシステムの運営会社である日本システム技術(株)のオペレーターが受電対応いたします。