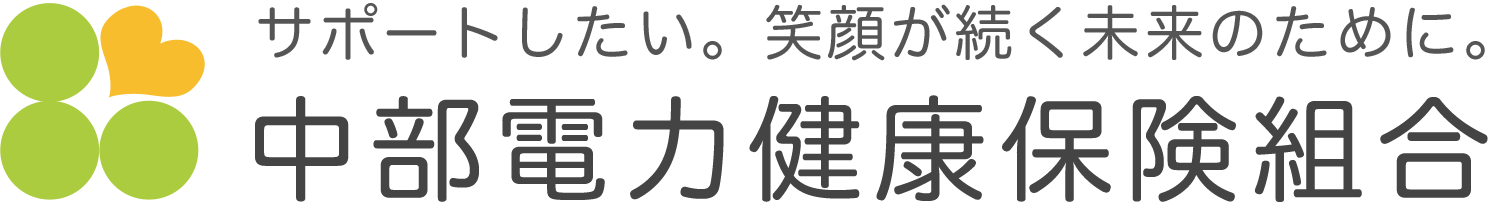誰もが経験する「めまい」症状を軽視せず
不調の原因を突き止めよう!
急に目の前がぐるぐる回ったり、ふわふわした感覚になったりする〝めまい〟。
「疲れているから」「寝不足が続いているから」などと安易に見逃していませんか。
症状が続くなら、病気を知らせる体からのシグナルかもしれません。
めまいは発症原因が複雑で、診断や治療が難しい症状です。
今回は原因不明や難治性のめまい症状の治療と研究に携わる聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院のめまいセンター長・瀬尾徹先生にお聞きしました。
平衡感覚の異常で起こるめまい 発症原因はさまざま
〝めまい〟と聞くと頭の中に原因があると思いがちですが、実は耳に原因があるケースが多いことをご存じですか。当院では2022年9月に「めまいセンター」を開設しましたが、めまいを訴えて受診された患者さんの6割ほどが耳に原因がありました。
めまいは体のバランス、いわゆる平衡感覚に異常が起こる症状で、その自覚症状は、目に映るものがぐるぐる回る〝回転性〟と、宙に浮かんだようにふわふわした感覚になる〝浮動性〟に大きく分けられます。
原因は、耳(末梢性(まっしょう)めまい)と脳(中枢性めまい)に大きく分けることができます。耳の一番奥、内耳には、平衡感覚を保つための重要な働きを持つ三半規管や前庭(耳石器)があります。この部位に異常が生じたことで発症するのが「メニエール病」「良性発作性頭位めまい症」「前庭神経炎」「突発性難聴」などです。適切な治療を早期に受けることができれば、多くのケースで改善します。
一方、脳に原因があるめまいには注意が必要です。激しい回転性のめまいとともに、ろれつが回らない、手足のしびれ、激しい頭痛などの症状が現れる場合には脳梗塞や一過性の脳血流障害、不整脈、狭心症などが原因である可能性があります。命に関わるケースもあるため、正確な診断が必要です。
耳や脳以外にも、不安や恐怖などこころの問題から起こるめまいに悩まされる人も近年増えています。たとえば大地震を経験した人が、揺れていないのに揺れているような感覚のめまいを感じることがあります。また病気治療のための服薬による副作用や、疲労や睡眠不足など生活スタイルの乱れから自律神経のバランスが崩れることなどがめまいの引き金になることもあります。
問診で症状を正確に伝えることが大切
このように、めまいはその発症原因が複雑な上、患者さんによって感じ方が異なるため、診断がとても難しい症状です。そのため問診がとても重要です。医療機関を受診する際は、どんなめまいなのか、いつ発症したのか、どれくらい続いているのか、どんなときに起こるのかなどを医師に正確に伝えてください。
検査では、多くのめまいで現れる「眼振(眼球が左右に揺れる現象)」の状態を調べるため、赤外線フレンツェル眼鏡などを用いて目の動きを調べます。当院では、内耳の耳石器の機能を調べる前庭誘発筋電図や三半規管の機能を調べるヘッドインパルステストなどの最新検査も行い、これまでは原因が分からなかっためまいの診断もできるようになりました。
治療は、メニエール病では主に薬物療法を行いますが、難治性の場合には内リンパ嚢(のう)開放術などの手術も行います。良性発作性頭位めまい症では、まず移動した耳石を元の位置に戻すエプレー法を行い、難治性の場合には三半規管の一部を手術で閉鎖する半規管遮断術を行うこともあります。
急にめまいが起こると誰でも慌ててしまうと思いますが、まずは転倒の危険がありますので安全を確保してください。無理をして動こうとせずに、立ち止まって座る場所を探しましょう。家や会社などで横になれる場所があれば周りを暗くして横になります。
しばらく安静にしても症状が治まらない場合は、すぐに医療機関を受診してください。受診科は耳鼻咽喉科や頭頸部(とうけいぶ)外科、脳神経内科などです。めまいを軽視せず、しっかり治療を受けることがとても大切です。
監修:瀬尾 徹先生
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 めまいセンター長
耳鼻咽喉・頭頸部外科部長 教授
Column
更年期以降の健康管理、気をつけたいこと
更年期以降の健康管理は、バランスの取れた食事と適度な運動が基本となります。
基礎代謝が落ちて体重が増えやすくなり、血圧やコレステロール値も上昇してきますので、塩分は控えめに、高カロリー食も避けて、腹持ちの良い根菜類や、血液をサラサラにするDHA・EPAといった必須脂肪酸を含むマグロ、イワシなどの青魚を積極的に摂るようにしましょう。
脂肪を燃やすにはランニングや水泳などの有酸素運動がお勧めです。それも、最初に筋力トレーニングを行うといいでしょう。なぜなら筋力がアップすると体の基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすくなるからです。有酸素運動はできれば30分以上は続けましょう。運動で最初に使われるのは糖質で、脂肪が燃えるのはその後だからです。
定期的な健康診断を受け、血圧やコレステロール値をチェックすることも重要です。
健康マメ知識
イソフラボンと女性ホルモン
更年期には女性ホルモンであるエストロゲンが急激に減少し、ホットフラッシュ、血圧やコレステロール値の上昇、骨量の低下などの症状が現れやすくなります。
そのため、エストロゲンと似た構造を持つイソフラボンを摂取することで、体内でエストロゲンと同様の働きをすることが期待できます。
イソフラボンは、納豆や豆腐、味噌、豆乳などの大豆製品に含まれているので、これらを食事で摂ることをお勧めします。安易にホルモン関連のサプリメントを服用すると、異常にホルモン値が上昇して不正出血などをもたらしたり、ホルモン依存性のがん(乳がんや子宮体がんなど)のリスクにさらされたりすることがあるからです。
イソフラボンの1日の最大摂取目安量は70~75mgとされています。例えば、イソフラボン含有量は、納豆1パック(約50g)で約37mg、豆腐半丁(約150g)で約30 mg、豆乳200mlで約49mgとなります。
※厚生科学研究「食品中の植物エストロゲンに関する調査研究(1998)」をもとに作成。
提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2023年11月号) **禁無断転載**
すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。
問い合わせ先
保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp